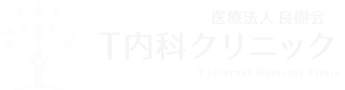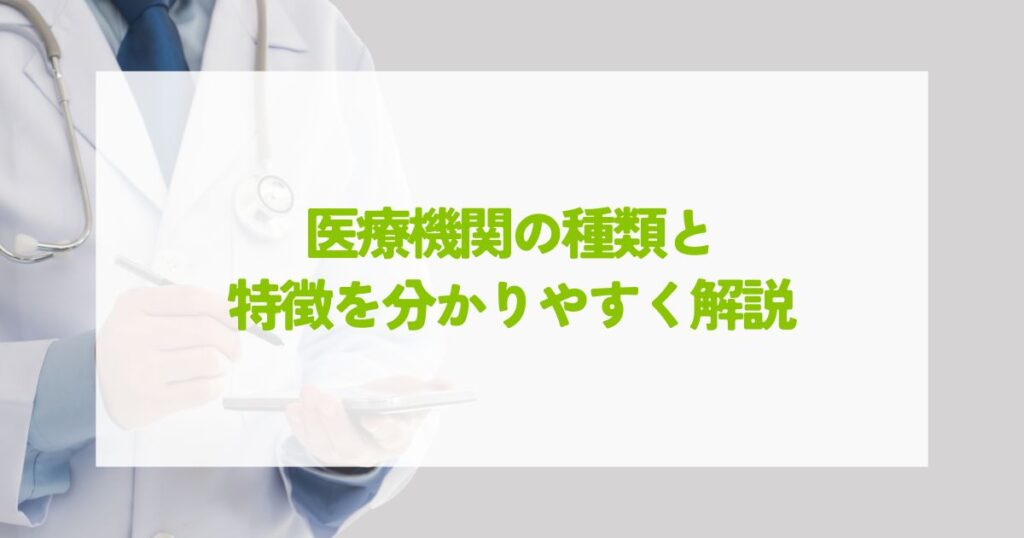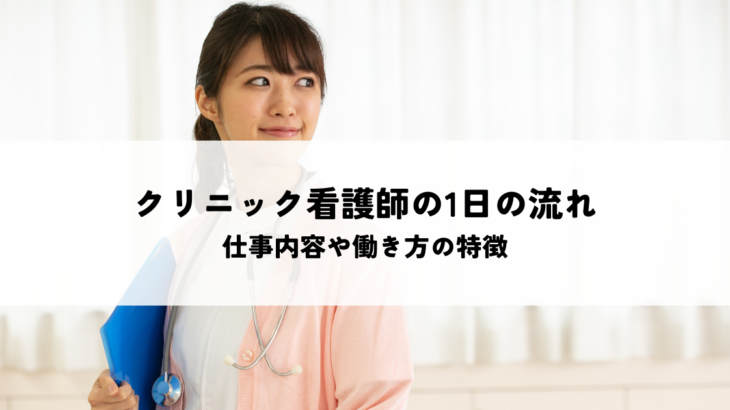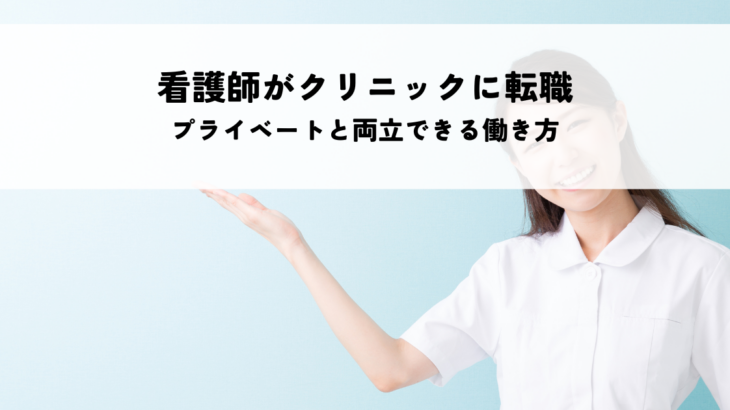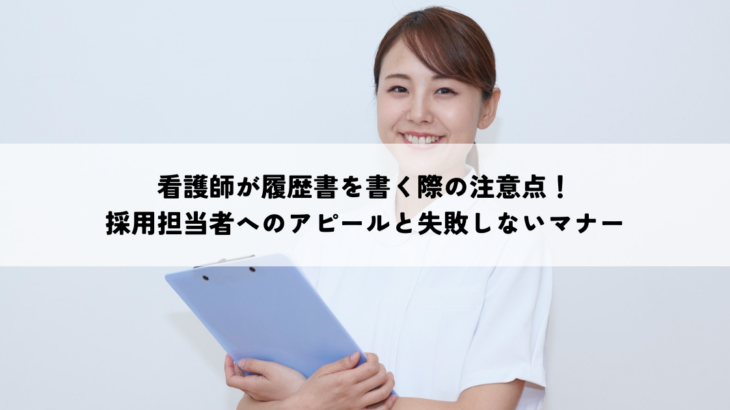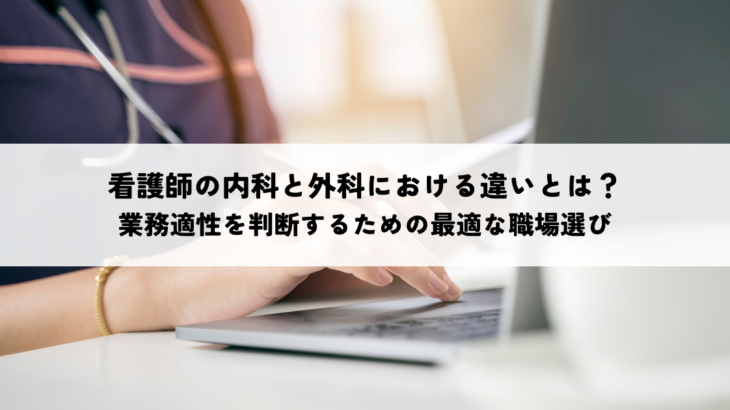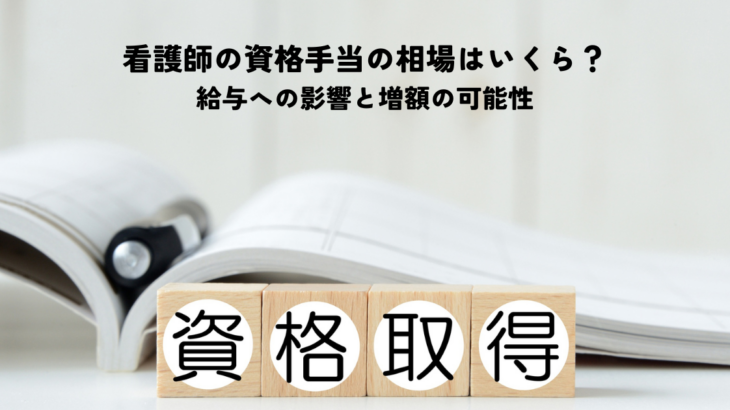日本の医療機関は多種多様であり、それぞれに役割や特徴があります。
病院と診療所は基本的な医療機関として知られていますが、その種類や規模、機能は実に多岐に渡ります。
今回は、これらの医療機関の種類と特徴について、分かりやすくご紹介します。
医療機関種類と特徴
病院の種類と特徴
病院は、病床数20床以上を有する医療機関です。
開設主体によって、国立病院、公立病院、公的病院、大学病院、一般病院などに分類されます。
また、病院は機能別にも分類されます。
地域医療支援病院は地域医療の中核を担い、かかりつけ医と連携して医療を提供します。
特定機能病院は高度な医療を提供し、医療技術の開発や研修にも力を入れています。
これら以外にも、急性期病院、慢性期病院、リハビリテーション病院、ケアミックス型病院など、様々な機能を持つ病院が存在します。
病床数によって大病院(400床以上)や中小病院(200床未満)と分類されることもあります。
診療所の種類と特徴
診療所は、病床数19床以下の医療機関です。
有床診療所(1~19床)と無床診療所があり、主に外来患者を対象とした診察や治療を行います。
医師1人でも開設でき、病院に比べて規模が小さいのが特徴です。
名称は「医院」「クリニック」「診療所」など、自由に付けることができます。
診療科名の標榜方法にも一定のルールがあり、患者にとって分かりやすい表示が推奨されています。
近年、有床診療所は減少傾向にありますが、在宅医療の拠点機能や終末期ケア、病院からの早期退院患者の受け入れといった役割が期待されています。
その他の医療提供施設
その他の医療提供施設には、助産所、薬局などがあります。
助産所は助産師が管理する施設で、妊婦や産婦のケアを行います。
薬局は医師の処方箋に基づいて薬剤を調剤する施設です。
近年では、かかりつけ薬局の推進も進められています。

医療機関の分類別の役割と選び方
急性期病院と慢性期病院の違い
急性期病院は、手術や専門的な検査・処置、救急医療などを行い、急な体調の変化に対応します。
一方、慢性期病院は、急性期治療後のリハビリテーションや継続的な療養を提供します。
専門病院の役割と受診のポイント
専門病院は特定の疾患や診療科に特化した医療を提供します。
専門医による高度な医療を受けられる一方、受診には紹介状が必要な場合もあります。
かかりつけ医と専門医の連携
かかりつけ医は、患者さんの健康状態を継続的に把握し、必要に応じて専門医への紹介などを行います。
専門医は、高度な医療技術を用いて治療を行います。
両者の連携が、質の高い医療提供に繋がります。

まとめ
今回は、医療機関の種類と特徴について、病院、診療所、その他の医療提供施設に分類して解説しました。
病院は病床数20床以上、診療所は19床以下と、病床数によって区別されます。
さらに、それぞれの医療機関は、開設主体や機能によって様々な種類に分類されます。